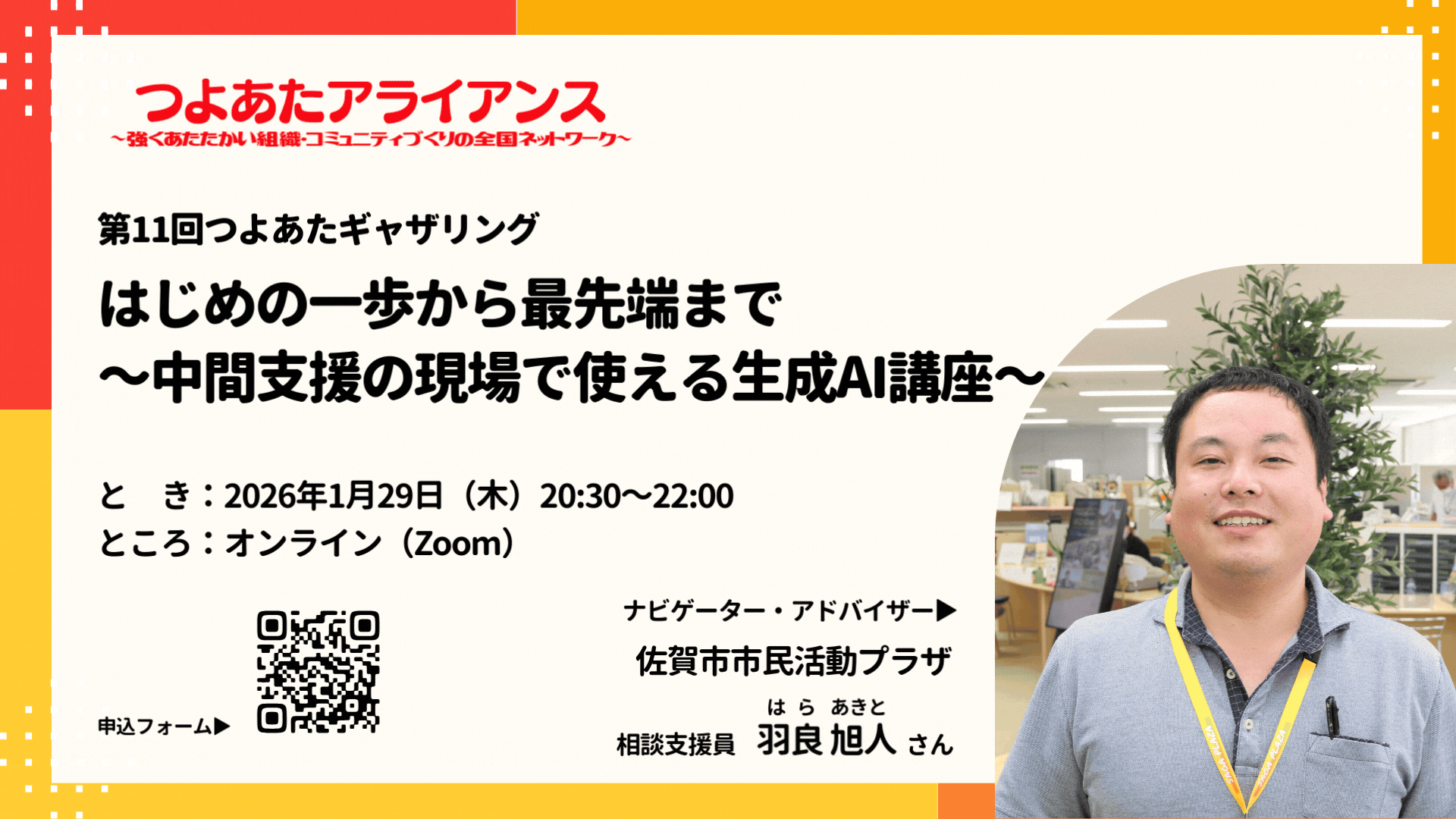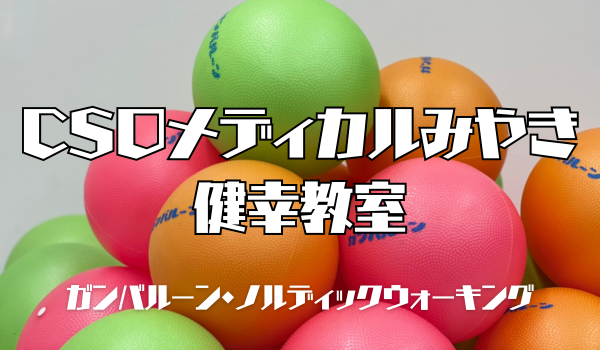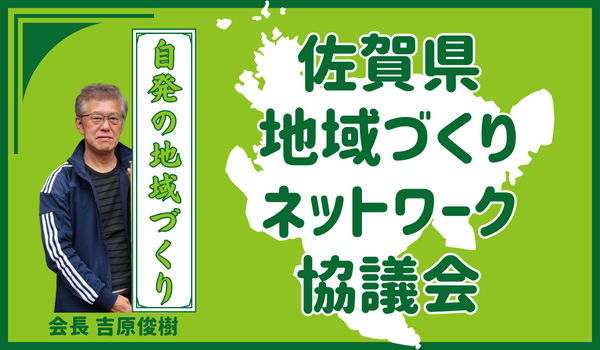当法人がオンライン配信を担当した7月4日の佐賀開催に続き、2025年9月10日(水)、認定特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン主催のアウトリーチ子育て支援セミナー「地域で身近な寄り添い型訪問支援を~親子に届く「傾聴」と「協働」の効果~」が開催されました。今回は佐賀から福岡市博多区の会場へ出張し、技術サポートを行いました。
前回のセミナーでは官民協働のあり方が共有されましたが、今回はさらに九州各地の実践に焦点を当て、従来の「待つ支援」では届きにくい孤立した親子への「アウトリーチ支援」の重要性とその効果について学び合う、貴重な機会となりました。
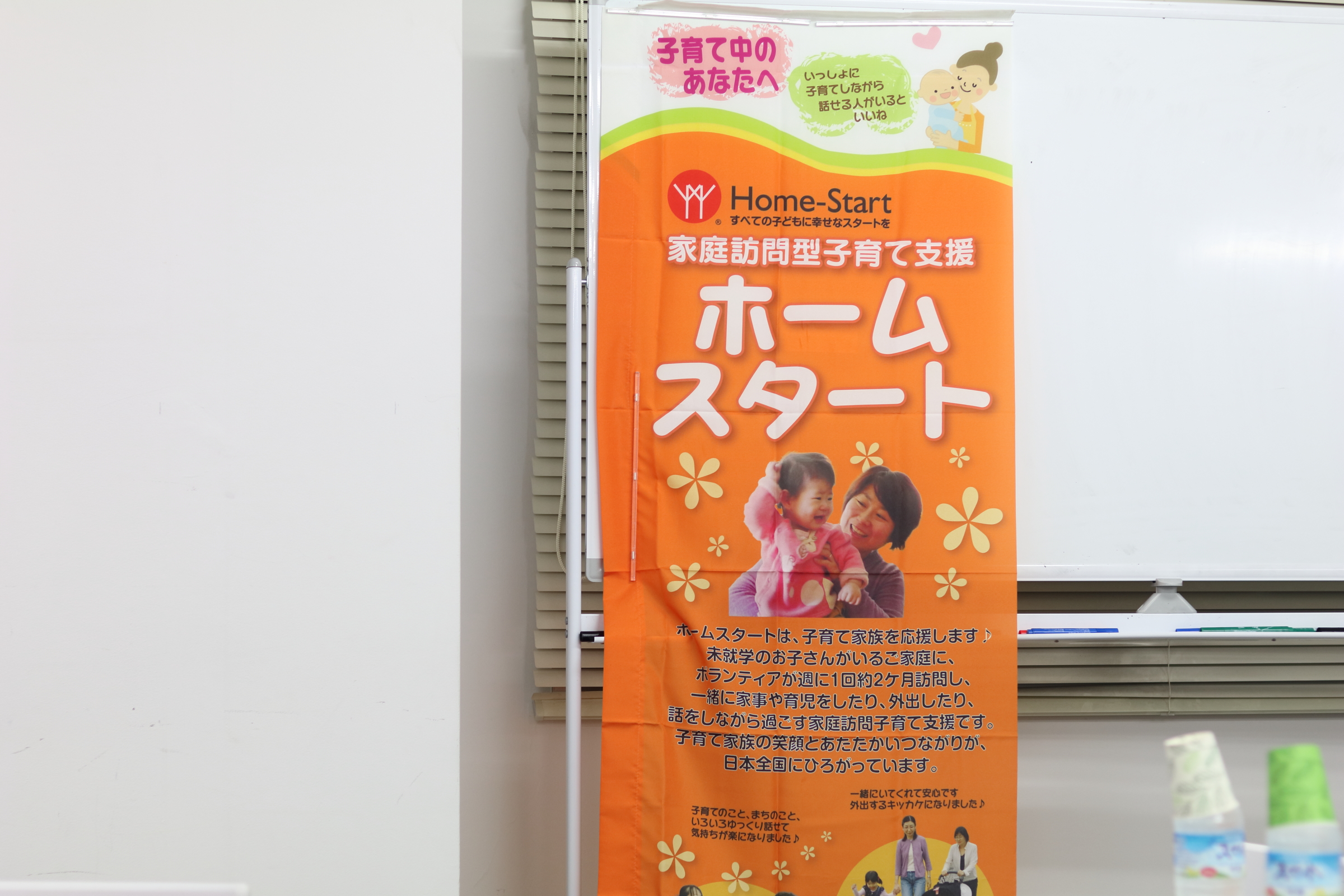

開催概要
- 日時:令和7(2025)年9月10日(水)14:00~16:00
- 会場:ふれあい会議室 博多東126号(福岡市博多区)
- Zoomミーティングによるハイブリッド開催
- 主催:認定特定非営利活動法人ホームスタート・ジャパン
- ※本セミナーは、日本財団の助成を受けて実施しています
- 【基調講演】「親子に寄り添う傾聴とアウトリーチ支援の意義」
- 河浦 龍生 氏
- 福岡市こども家庭支援(はぐはぐ)センター長
- 佐賀市要保護児童対策地域協議会スーパーバイザー
- 社会福祉士
- 河浦 龍生 氏
- 【活動報告】九州での寄り添い型訪問子育て支援の実践事例紹介(ホームスタート)
- 福岡県北九州市
- 認定NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン
- 大分県豊後高田市
- NPO法人アンジュ・ママン
- 佐賀県佐賀市
- ホームスタート・さが(諸富地区社会福祉協議会)
- 福岡県北九州市
- 【パネルセッション】


基調講演
「親子に寄り添う傾聴とアウトリーチ支援の意義」
講師: 河浦 龍生 氏
- 福岡市こども家庭支援(はぐはぐ)センター長
- 佐賀市要保護児童対策地域協議会スーパーバイザー
- 社会福祉士
河浦氏は、少子高齢化や経済格差、ジェンダーバイアスといった現代社会の課題が、子育て家庭の孤立を深刻化させていると指摘。こうした状況で、「支援者が専門知識を教える」という一方的な関わりではなく、親が本来持つ力を引き出す「エンパワメント」の視点が不可欠であると説きました。
その核となるのが「傾聴」と「協働」です。ただ話を聞くのではなく、相手の感情や価値観を尊重し、共に考え、行動する「伴走型」の関わりそのものが、親の心を癒し、自己肯定感を育む「治療的な意味を持つ」と強調。特にホームスタートのようなボランティアによる支援は、専門職とは異なる「地域の身近な存在」として、親が心を開きやすいという大きな利点があると語りました。
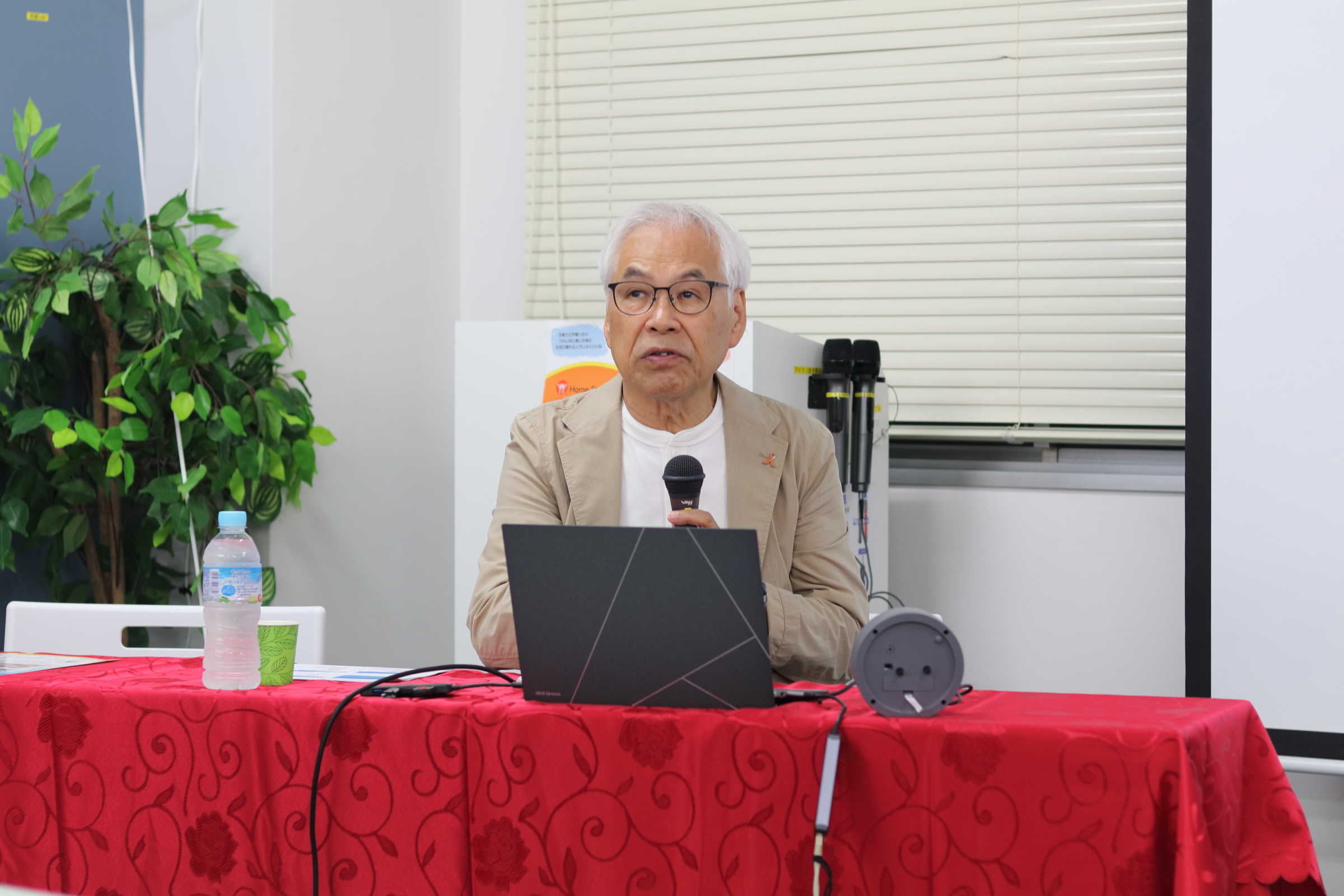

実践事例紹介
基調講演に続いて、九州3県で活動するホームスタート実践団体から、特色ある取り組みが報告されました。
福岡県北九州市:袋野 茉緯未 氏
フードバンク活動を母体とする同団体。袋野氏は、食料支援を通じて出会う家庭が、経済的な困窮だけでなく、精神的な孤立という複合的な課題を抱えている実態を報告しました。
「食べ物があれば解決するわけではない。話を聞いてくれる人が必要だ」という切実な声に後押しされ、ホームスタート事業を開始した経緯を説明。「食」をきっかけにつながった家庭にホームビジター(ボランティア)が訪問し、じっくりと話に耳を傾けることで、ある母親からは「初めて自分の話を聞いてもらえた」と涙ながらに感謝されたエピソードを共有。食品ロス削減という環境的アプローチと、子育て支援という福祉的アプローチの両輪で、拠点に来られない家庭にも支援を届ける活動の重要性を語りました。


大分県豊後高田市:小川 由美 氏
活動15年目を迎える同団体。小川氏は、過疎化が進む地域において、子育てひろばという「拠点」とホームスタートの「訪問」を両輪で展開することで、切れ目のない支援を築いてきた実践を報告しました。
ひろばに来られなくなった親子に訪問支援で関わり続けたり、逆に訪問をきっかけにひろばにつながったりと、柔軟な対応を紹介。長年の活動を通じて、かつての利用者が経験を活かしてボランティアになるという「支援の担い手の循環」が生まれていることを共有し、「地域に顔見知りがいる安心感」を育むことが、地域全体の子育て力を高めることにつながると述べました。


佐賀県佐賀市:野口 洋子 氏
- ホームスタート・さが/オーガナイザー
- 諸富地区社会福祉協議会
前回の佐賀開催セミナーにも登壇した野口氏は、行政や民生委員、学校など多機関との連携の重要性を改めて強調しました。
特に印象的だったのは、家庭内暴力(DV)という深刻な課題を抱え、お子さんが学校で問題行動を起こしていた家庭に、野口氏自身がビジターとして訪問した事例です。
当初は心を閉ざしていた母親が、訪問を重ねるうちに少しずつ心を開き、それまで緊張関係にあった子どもがお母さんに甘えられるように。その変化を目の当たりにした母親も、子どもへの言葉遣いが優しくなり、最終的には行政の支援を受けながら離婚を決意し、親子で新たな生活へと踏み出しました。
この事例から、ただ「共にいる」という寄り添いが、家族が本来持っている力を引き出し、自ら変わっていく大きなきっかけになることを力強く語りました。


パネルセッション
3団体の具体的な実践報告を受け、パネルセッションへと移行。モデレーターの山田幸恵氏(ホームスタート・ジャパン理事・事務局長)の進行のもと、活発な意見交換が行われました。
まず、基調講演を行った河浦氏が、3団体の報告に対して「三者三様で、それぞれの地域に根差した素晴らしい活動だ」と感嘆の声を上げました。特に、ホームスタート・ライフアゲインの「切れ目のない支援体制」、アンジュ・ママンの「行政かと見まがうほどの多機能性と行動力」、そしてホームスタート・さがの「行政から事業を受託しているという連携の深さ」をそれぞれ高く評価しました。
支援の核心にある「治療的な意味合い」
セッションの中心的なテーマとなったのは、「寄り添う」という行為が持つ意味です。河浦氏は、「つらい時、苦しい時に、ただそばにいてくれるだけで心が安らぐ。これは専門家でなくても誰もができる、非常に治療的な意味合いを持つ関わりだ」と解説。専門的な介入だけでなく、地域住民による温かい眼差しや存在そのものが、孤立しがちな親子の心を癒やす大きな力になると強調しました。
実践者が語る、親子の「変化」の瞬間
この「寄り添う支援」が具体的にどのような変化を生むのか、各団体のオーガナイザーが現場のエピソードを交えて語りました。
袋野氏(北九州市)
夜泣きで疲れ切っていた双子の母親の事例を紹介。「初対面では表情が硬かったお母さんが、訪問を重ねるうちに笑顔を取り戻し、『ビジターさんと話せるから、また一週間頑張れる』と話してくれた。その表情の変化こそが、この活動の価値を物語っている」と語りました。
小川氏(豊後高田市)
市の「利用者支援事業」のコーディネーターとして、保健師の初回訪問に同行するケースに言及。「専門職と一緒に入ることで、その家庭の本当のニーズが見えてくる。そこからホームスタートを含む、その親子に合ったオーダーメイドの支援につなげることができる」と、多機関連携の入り口としての役割を説明しました。
野口氏(佐賀市)
「私の気持ちがわかるの?」と当初は心を閉ざしていた母親が、ビジターとの関わりを通して少しずつ自分を語り始め、最終的には自身の力で生活を立て直す勇気を得た感動的な話を共有。「私たちは何もしていない。ただ話を聴いていただけ。でも、それでお母さんが本来持っている力に気づき、子どもとの関係まで変わっていった」と、支援のあり方を振り返りました。
こどもまんなか社会に必要な支援
議論の最後に河浦氏は、「アウトリーチ支援こそが、まさに『こどもまんなか社会』のど真ん中にあるべき活動だ」と力強く締めくくり、地域全体で親子を支える社会の実現に向けた、ホームスタート活動の重要性を改めて示唆しました。




全国の支援者をつないだオンライン配信
7月の佐賀開催に続き、今回も当法人はオンラインCSO支援の一環として、福岡の会場から全国へセミナーの様子をハイブリッド形式で配信するサポートを行いました。
この取り組みにより、北は東北から南は九州各地まで、行政、医療、福祉、NPOなど多様な立場の支援者がオンラインで集結しました。
セミナー終了後には、オンライン参加者同士での意見交換の時間が用意されており、距離を感じさせない一体感のある学び合いの場となるように工夫されていました。
今後の展望
佐賀県CSO推進機構は、これからもCSO(市民社会組織)の活動をICTで支える「オンラインCSO支援」を推進してまいります。イベントや会議のハイブリッド開催サポートを通じて、時間や距離といった物理的な制約を取り払い、誰もが学びや交流の機会に参加できる「参加のバリアフリー」を実現します。このような取り組みを重ねることで、CSOの活動基盤を強化し、ひいては地域社会全体の活性化に貢献していく所存です。
お問い合わせ先
特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構
(CSO経営支援事業部 オンラインCSO支援)
- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階
- TEL:080-4282-8061(事業部用携帯)
- FAX:0952-40-2011
- E-mail:cso.sprt@min-nano.org
- Facebook:https://fb.com/sagacso/
- Instagram:https://instagram.com/sagacso/